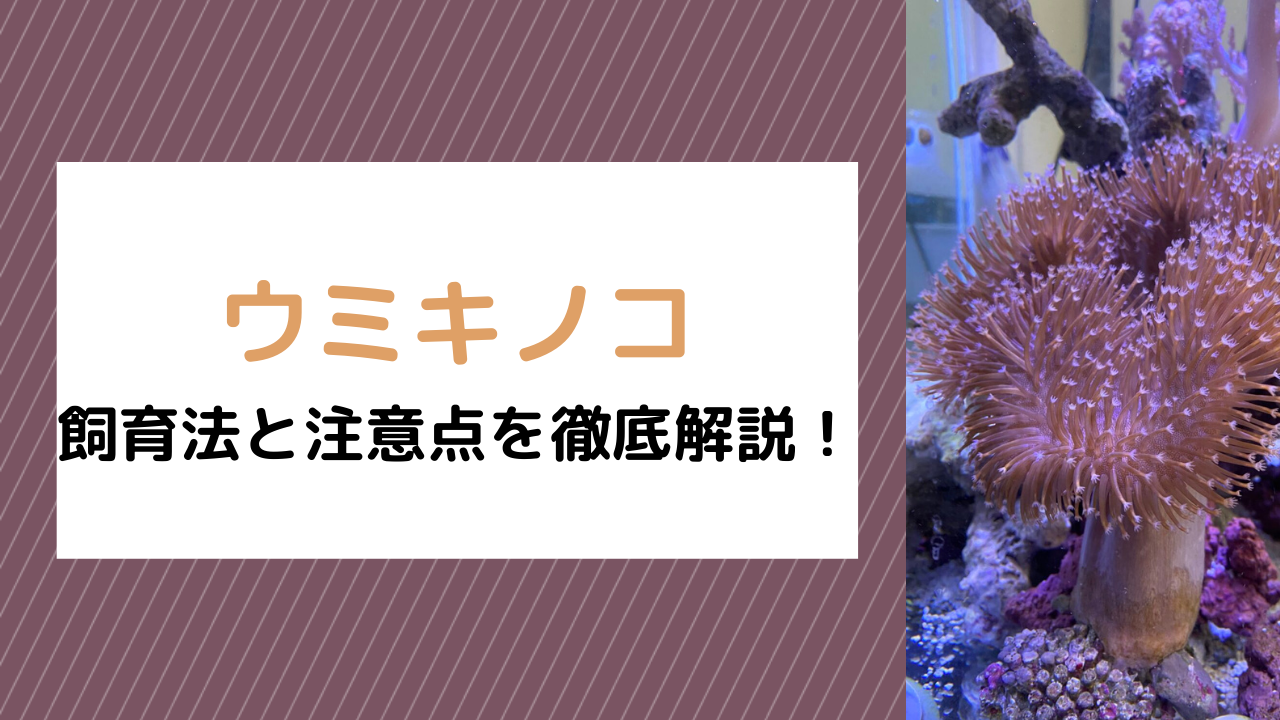【父島】オガサワラベニシオマネキを干潟で観察!〈マリラバ生物探訪〉
オガサワラベニシオマネキ Uca boninensis

オガサワラベニシオマネキ Uca boninensis (Shih, Komai and Liu, 2013)
目:十脚目
科:スナガニ科
属:Uca属

父島二見湾奥の小河川の干潟に生息する小笠原諸島固有種。今のところ確認されているのは父島のみで、生息地は非常に狭く、総個体数は非常に少ないと推定されています。
干潮時に干潟の砂泥の上に出てきて、砂表面の珪藻などの有機物を食べています。
良く晴れた暖かい日にはたくさんの個体数が干潟に出てきて活動している印象です。オスは頻繁に大きい方のハサミを振り上げ、メスに求愛しています。

今日の父島 〜オガサワラベニシオマネキのはさみふりふり〜 pic.twitter.com/YTo2HfYFot
— りるたき (@rirutaki_sakana) March 3, 2025
このカニはものすごく神経質なので、写真を撮るのはクソむずいです。半径3m以内の個体はカメラを少し動かしただけで速攻巣穴に引っ込みます。
自然体の行動を観察するためには、観察ポイントについてからしばらく身動き一つとらずに我慢する必要があります。
そこを何とか我慢して身を潜めていると…



こんな姿を見ることができます。この後乗り上げられたメスはオスを振りほどいて逃げていきました。
また、個体によっては背中の甲羅の模様が翡翠のように美しいです。

実にかわいらしいです。
案外探せばすぐ見つかるような場所にいるので、父島で晴れた干潮時にはぜひ探してみてください!

なお、身体的特徴、生息地、その他DNAに関する情報などについては
Shih, H.-T., T. Komai, and M.-Y. Liu (2013) A new species of fiddler crab from the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan, separated from the widely-distributed sister species Uca (Paraleptuca) crassipes (White, 1847) (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Ocypodidae). Zootaxa 3746(1):175–193.
に詳しく記載があります。気になる方はぜひ。
ちなみに、どうやらオガサワラベニシオマネキの祖先の個体群は南太平洋のコロニーから不安定な海流に乗って流れてきた事が示唆されているようです。
実際小笠原諸島付近の海流は離散的で、隣接する島々からの個体群(カニ以外も)の遺伝的交流の障壁として重要な役割を果たしているとか。
小笠原諸島の動植物の固有性の高さは「海洋島」というだけで形成されたものではなく、周辺の海流の状況も大きく関係しているのかもしれません。

またオガサワラベニシオマネキは比較的高い遺伝的多様性を示します。
これはオガサワラベニシオマネキの祖先が小笠原諸島にやってきた頃(更新世)の古環境が温暖な環境に適応したシオマネキ類の生息環境としては低温・乾燥環境であったことと関係しているようです。
というのも、ベニシオマネキにとって非常に環境ストレスが大きな環境で生育していたことで、遺伝子の組み換え頻度と突然変異率が増加し、進化速度が上がった可能性が示唆されているのです。

とまあ小笠原諸島の狭い領域に生息するカニの進化にも、とても大きな自然界の流れが関わっているのです。
実に興味深いベニシオマネキの世界。あなたも覗いてみてください!
※オガサワラベニシオマネキは非常に狭い生息環境において、非常に少ない個体群が細々と生息しています。
彼らを守るため、観察する際は以下の点を意識しましょう。
・観察時にはむやみに生息環境を荒らさないこと(巣穴を踏んでしまわないように注意!)
・観察後も生息環境をむやみにネット上などに公開しない(論文を読めばわかる事ではありますが…)
彼らの貴重な生息環境を守るため、何卒よろしくお願いします。